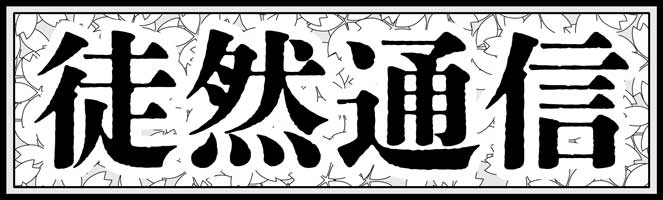1月7日といえば、七草粥です。

私もいただきました。
味はさっぱりしていて
かつ薬草・ハーブの香りもあり、
なんか体に良いものを摂取している感じがしました。
今回は七草粥の由来や効果をまとめてました。
七草粥とは 1月7日は「人日」の節句
七草粥とは人日の節句(1月7日)の朝に食べる
日本の行事食です。
1月7日は、人日の節句で、五節句のひとつです。
五節句の一覧
- 人日(じんじつ):1月7日 – 別名「七草の節句」
- 上巳(じょうし):3月3日 – 別名「桃の節句」
- 端午(たんご):5月5日 – 別名「菖蒲の節句」
- 七夕(しちせき):7月7日 – 別名は「笹の節句」
- 重陽(ちょうよう):9月9日 – 別名「菊の節句」
七草粥 なぜ食べるの?
七草粥を食べる理由は以下の通りです
- 邪気を払うため
七草粥に使われている春の七草は、早春一番に芽吹くためそう信じられています。 - 正月から日常の食生活に戻る区切りのため
- 正月の飲み食いで疲れた胃を休めて野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うため
七草粥の由来は?
時代は古く、中国より伝わり、
日本では平安時代の初期に宮中の行事となり、
江戸時代になって庶民に広まりました。
古代の粥は「七種粥」と言われ、
- 米
- 粟
- きび
- ひえ
- みの
- ごま
- 小豆
でした。
今の7種類になったのは、
鎌倉時代になってからだと言われています。
- せり
- なずな
- ごぎょう
- はこべら
- ほとけのざ
- すずな
- すずしろ
古代の中国では、
1月7日は官職の昇進を決める大切な日であり
立身出世を願ったそうです。
日本では、若い生命力を摘みいただくことで、
健康に過ごせるとか、
無病息災を願いって
多くの地域に広まりました。
こちらもCHECK
-

-
演技力が半端ない!出光興産の創業者がモデルの「海賊とよばれた男」を観て感じたこと。
恥ずかしながら、この映画を知るまでは知りませんでした。 石油大手、出光興産は九州発だったのですね。 出光 佐三(いでみつ さぞう、1885年8月22日 – 1981年3月7日)は、明治から戦後にかけて …
続きを見る