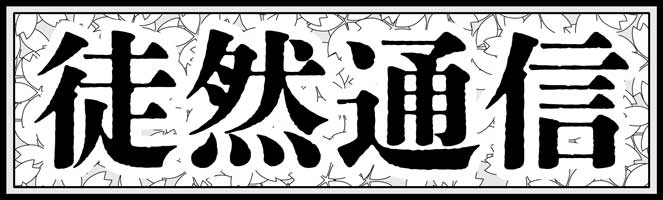江戸時代といえば対外的には鎖国が有名です。
国内事情も同じく時代劇の関所のイメージ通り、
庶民の国内の移動も制限されていました。
江戸時代庶民の旅行は禁止!自由な移動はここ最近のこと
突然ですがクイズです(じゃかじゃん♪)
現在2時間30分あればどこまで行けるでしょうか?
チッ、チッ、チッ、チッ
新幹線では大阪まで、
飛行機では沖縄まで、
東京から行くことができます。
もちろんお金も必要ですが、
気分転換に旅行をしようと思えば、
数時間で目的地に行けます。
交通手段の進歩は、
我々に多大な恩恵を与えてくれました。
一方、江戸時代は移動手段といえばもっぱら、徒歩です。
日帰りツアーで温泉に浸かってなんて話はありえません、
旅行といえば何日もかけるものでした。
しかも、庶民が自由に国内を移動できるようになったのは、
実はここ最近、明治時代以降になってからのことです。
江戸時代 人々の自由な移動は制限されていた
先述の通り、江戸時代は武士や庶民の区別なく、
人々の自由な移動は制限されていました。

通行手形がなければ、
関所の門をくぐることはできません。
今では想像しずらいですが、
関所破りは重罪で磔の刑(つまり死刑)に処されました。
通行手形とは
通行手形とは、
江戸時代の日本で人が旅をしようとするときに、
許可を得て旅行していることを証明した物です。
旅行中所持していることを義務付けられていますので、
現代の通行証や日本国旅券(パスポート)に相当します。
シャレではないのだが、
当時の藩は半独立国家のようなものです。
現代人の感覚で言えば、
ビザを取ってパスポートを持って、
海外に行くような感じだったのだと思います。
江戸時代旅行は禁止だが神社仏閣巡りは例外
庶民の移動が制限されていた江戸時代の旅行。
では、誰もが生まれ故郷や領地に缶詰だったかというと、
そうでもなかった様子です。
大名行列と言えば、
一般の通行人は道端へ避けて下座しなければなりませんでした。
ましては頭をあげたり、
横切ったり無礼があれば、
すぐさまその場で、切捨てられてもおかしくありません。

そんな大名行列にも例外があります。
医者と産婆は横切って良かったのです。
人命に関わることなので、
寛容なとことが我が国の文化の素敵なところです。
庶民の移動の制限には例外がありました。
それは、神社仏閣をめぐる
信仰目的の旅であれば可能だったようです。
- 伊勢参りの旅については例外的に無条件で許されていた
- その他、日光東照宮、善光寺など、有名寺社の参詣もおおむね許されていた
つまり当時は、
旅行=神社仏閣巡りだったと言っても過言ではありません。
江戸時代神社仏閣巡り代表格はやっぱり伊勢の神宮!
代表的なのは三重県の伊勢の神宮(正式名称は「神宮」)の
「おかげまいり」です。

文政13年(西暦1830年)には5ヶ月足らずで、
427万人の参宮者があったとの記録が残っています。
伊勢の神宮は、
今も昔も大人気のパワースポットなのです。
最近では女子旅や御朱印集めなども人気です。
本家の神社本庁が資格試験まで出すくらいに
神社巡りは盛り上がっています。
まとめ:神社仏閣巡りは日本人のDNAに刻まれているのかも
そういえば私も、
旅行に出かけた際は、
現地の神社仏閣+お城を自然と見てまわっています。
今でも旅行と言えばなんとなく、
その地の神社仏閣を見てまわる風潮があります。
これは我々日本人のDNAに、
代々刻まれてきた記憶なのかもしれません。
こちらもCHECK
-

-
やっぱ古事記っしょ!「神話を忘れた民族は100年以内に滅びる」
日本の神話といえば古事記 「神話を忘れた民族は100年以内に滅びる」と言ったのはイギリスの歴史学者アーノルド・J・トイン氏です。 日本人にとっての神話は「古事記」です。ヤマタノオロチや岩戸隠れの話など …
続きを見る